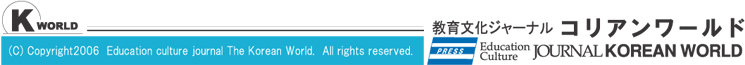|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お互いの健闘にエールを送り合う出席者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――最後に若い世代へのメッセージをお願いします。 アン 近くの外国人からお友達になって、お互いが相互理解をするようにならないと、共存というのはできないだろうなと思います。だから若い人たちには、どんどん近いところから国際社会を広げていく目を養っていってほしい。たくさん情報があり、惑わされやすい分、近くの外国の人から手をつないだり、人間と人間同士のお付き合いをして、自分で感じる目を養ってほしいと思います。在日は在日で自分が感じた今の社会と、自分のできることという可能性を感じて、夢をもって前に向かってほしい。そして諸先輩方ともっとコミュニケーションをとって、社会に役立つ人間になるよう、自分に付加価値をつけて頑張ってほしいですね。 今は在日だからといって閉ざされている分野は大分減りました。何でもやってみて若いうちに吸収し、広い視野を持てるように、見たり聞いたり学んだりをいっぱいやって、自分の可能性を追求して、夢にむかっていってほしい。自分は在日だからとか、これぐらいしかできないからと自分でフタをせずに、突き抜けてほしいなと思います。 国本 これからの若い世代、夢をもっていきてほしいですね。僕はプロ野球選手になりたいという夢をもって一生懸命頑張っていたんですが、気が付けば地方議員になっていました。自分の人生って、どう転んでいくか分からないですよね。 どう転んでいくかは分かりませんが、努力をしていけば、必ず報われますし、それに対して必ず自分の味方になってくれる人が現れます。それは在日とか日本人とか国籍は関係なく、必ず出てきます。辛いこともあるかもしれないけど、若い人たちには努力し続けていってほしいなと思います。 白 肩肘張る必要はない、ということでしょうか。私もまさか自分が政治家になるなんて夢にも思っていませんでしたしね。ただ、今考えてみると、人生無駄はないなと思います。やっぱり学んでいるんですよ。いろいろな経験を積んで、いまの自分があるわけですから。 ――ありがとうございました。皆さんの一層のご活躍を期待します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||